労災保険の始まりはいつから?歴史について
※学生向けの教科書(保険など)については税金や保険を学ぼうを参照。

戦前の日本は、経済の発展・近代化が進むとともに労災が多発し、労働運動が激化しはじめていました。
※労働運動とは:健康や生活の安定などをもとめ、労働者たちが集団で抗議する運動。
当時の日本には労災を予防するような法律は無かったため、労働者の健康と生活の安定をもとめる運動が大きくなりはじめたのです。
この問題に対処するために1905年に鉱業法、1911年に工場法をつくり、工場や炭鉱で働く人々の「仕事上の病気・ケガ・死亡」を補償する決まりをつくりました。
炭鉱や工場で働くひとは守られましたが、土木・建築などの労災が発生しやすい職業を補償する法律はこのときまだありませんでした。
では次に、労災が建築業などにも適用され始めた時代について下記で説明していきます。結構遅れて制定されます。
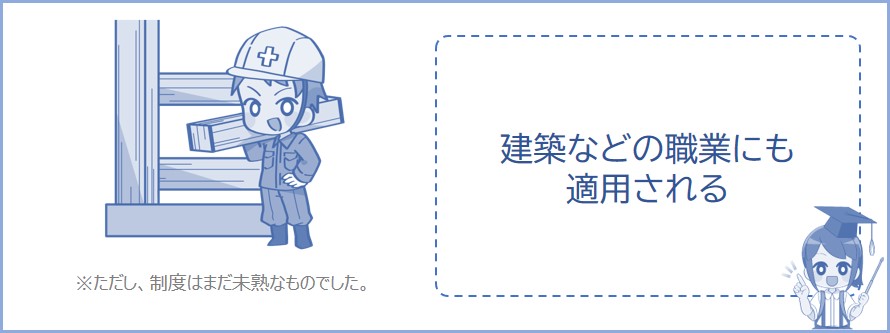
土木・建築などの労災を補償する法律の制定は見送られていたのですが、1931年になると「労災
しかし、このときの制度は「補償のレベルが低い」「適用範囲が狭い」ことや「使用者が労働者を助けてあげている」といった思想で成り立っていたため、制度としてはまだ未熟なものだったそうです。

制度として未熟だった労災
そして、1947年に労災保険制度が誕生しました。
これによって適用範囲や補償内容も改善されたのです。
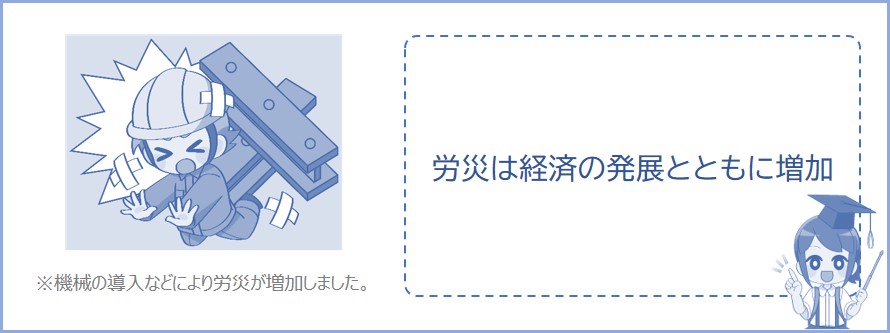
日本の産業が漁業や農業が中心だったころから、おそらく労災は起こっていました。ただその頃は「労災は労働者の不注意」と考えられていました。
その後、経済発展がきっかけで労働に機械が導入されたことや、長時間労働による疲労で労災が多発したことにより、「労災は労働者の不注意」という思想から「労災の責任は使用者にある」という思想に変化していきました。
そして「他人を雇用して職業を営む人は、雇用された人(従業員)が被害にあったときに補償すべき」という思想の制度(労災保険)が誕生したのです。
※労災保険が私たちにどんなことをしてくれるのか 万が一のときのために把握しておきましょう。
※小中学生に向けた内容は→労災保険ってなに?を参照。
※年金制度については年金制度の始まりはいつから?を参照。
※ほかの歴史については制度の始まり一覧を参照。
※参考文献:横山和彦, 田多英範, 日本社会保障の歴史, 1991年
雇用保険の始まりはいつから?歴史について
税金?保険?何もわからない!知っておかなきゃいけないポイントを解説
 しらべたい内容を探す
しらべたい内容を探す
















