育休とは?期間はいつまで?条件は?わかりやすく解説
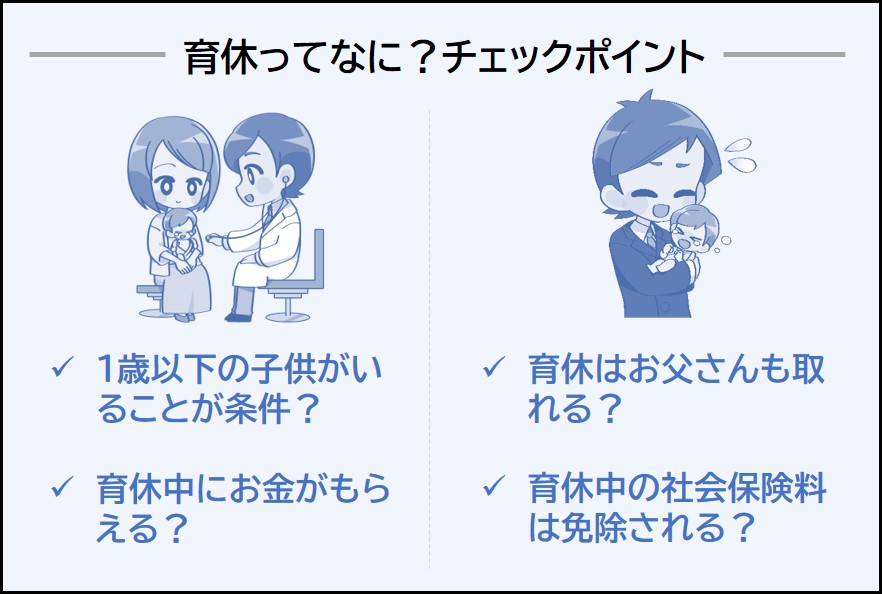
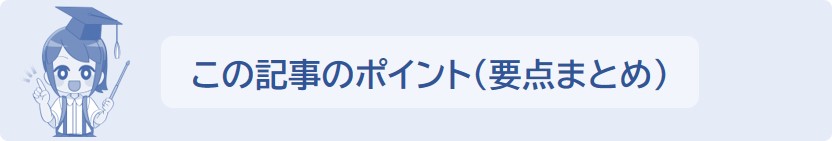
▶育休の条件は?社員じゃなくても取れるの?
1歳未満のこどもがいれば、正社員じゃなくても育休は取得できる(パートなどの場合はその他条件あり)。さらに、育休で休んでいる期間があればお金が支給される場合がある。
※くわしくは下記で説明しています。
※育休中にもらえるお金については下記で説明しています。
▶育休はいつまで休めるの?
育児休業が取れる期間は子供が1歳になるまで。条件にあてはまれば延長できる場合もある。
※くわしくは下記で説明しています。
▶夫婦両方とも育休を取れるの?
パパも育休を取れる。夫婦ともに取得すれば期間が1歳2か月までに伸びるメリットがある。
※くわしくは下記で説明しています。
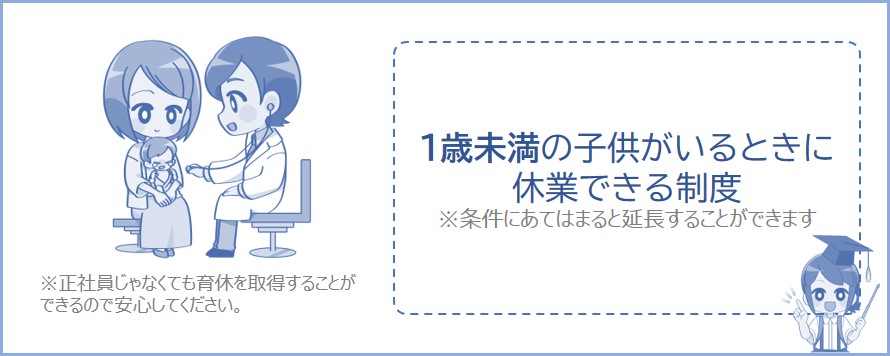
育児休業制度(育休)とは、1歳未満の子どもを育てるために休業することができる制度です。
条件にあてはまれば「育児休業」として仕事を休むことができます。また、1人の子どもについて、父・母ともに2回取得することができます。
※2022年10月から父母共に2回に分割して取得できるようになりました。
※雇われて働いている方は育休を取得できる権利が法律(育児・介護休業法、労働基準法、男女雇用機会均等法)で定められています。くわしくは両立支援制度とは?を参照。
※2025年4月以降も内容が見直しされました(前よりも柔軟になりました)。

育休は条件にあてはまれば正社員じゃなくても取得できます。
男性・女性に関わらず以下の条件にあてはまれば育休を取得することができます。
1歳に満たない子どもを育てている男女労働者(日々雇用を除く)であること。
※有期契約労働者(パートやアルバイトをしている方、派遣の方など)は子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
※2022年4月から「同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること」という条件は無くなり、有期契約労働者が育休を取得しやすくなりました。くわしくはこちらのお知らせを参照。
※参照:厚生労働省育児・介護休業法のあらまし
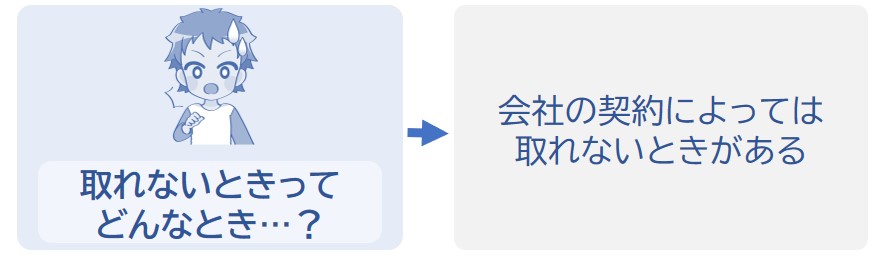
次のような労働者について「育児休業をすることができないこととする労使協定(会社との契約)」があるときは、事業主は育児休業の申出を拒むことができ、拒まれた労働者は育児休業を取得できません。
- 雇用された期間が1年未満の労働者
- 1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者(1歳6か月までの育児休業の場合は、6か月以内)
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
※参照:厚生労働省育児・介護休業法のあらまし
では次に、育休が取れる期間はどれくらいなのかについて下記で説明していきます。ずっと育休できるわけではありません。
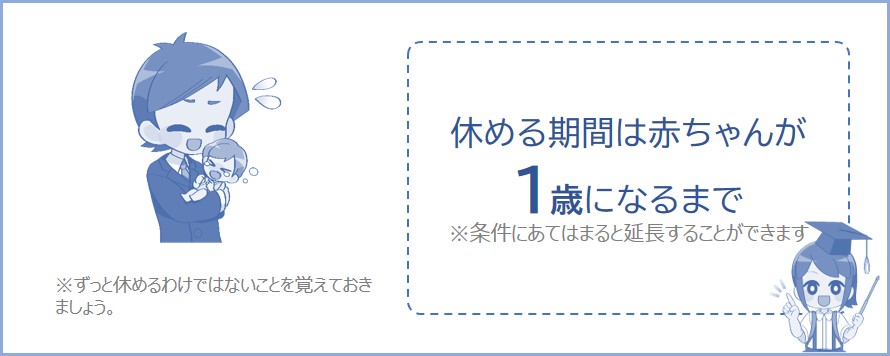
育休は子供が大きくなるまで取得できるわけではありません。
育休をとれる期間は子どもが1歳になるまで(誕生日の前日まで)です。
また、父母共に1歳までの育休を2回に分割して取得することができます。産後パパ育休を取得した方も育児休業は2回に分割して取得できます。
※ママパパ2人とも取得すれば1歳2ヶ月になるまで育休が可能になります。くわしくは下記で解説。
保育所に入れたいけど入所できないなどの場合、1歳6か月または2歳になるまで育休を延長することができます。
※育休の延長をするときは事業主に申請することになります。延長が認められれば育児休業給付金がもらえる期間も延長されます。
次のいずれかにあてはまる場合、1歳6か月または2歳まで育児休業期間を延長することができます。
※参照:厚生労働省育児・介護休業法のあらまし
- 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合で、1歳を超えても当面その実施が行われない場合
- 1歳以降、子の養育をする予定であった配偶者が死亡・負傷等の事情によって、子を養育することが困難になった場合
- 産前・産後休業、産後パパ育休または新たな育児休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、産前・産後休業、産後パパ育休または新たな育児休業の対象となった子が死亡したときまたは他人の養子になったこと等の理由により労働者と同居しなくなったとき。
- 介護休業の開始により育児休業期間が終了した場合で、介護休業の対象となった対象家族が死亡したときまたは離婚、婚姻の取消、離縁等により対象家族と労働者との親族関係が消滅したとき。

育休はお母さんだけじゃなくお父さんも取ることができます。
夫婦両方ともに育休を取る場合、条件にあてはまれば子どもが1歳2ヶ月になるまで育休の期間を延長できるんです。
したがって、育児休業給付金がもらえる期間も長くなるので、通常よりもお得です。
パパ・ママ育休プラスを取得するときは事業主に申請することになります。
※くわしくは育児休業給付金とは?手取り金額など解説で説明しています。
- 配偶者が、子が1歳になる日以前に育児休業を取得していること
- 育児休業開始日が、子の1歳の誕生日以前であること
- 育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業の初日以降であること
※2022年10月から育休には産後パパ育休も含みます。
育休中に夫妻で育児休業給付金をもらうつもりの方にとってはお得な制度なので、パパ・ママ育休プラスを申請することをオススメします。
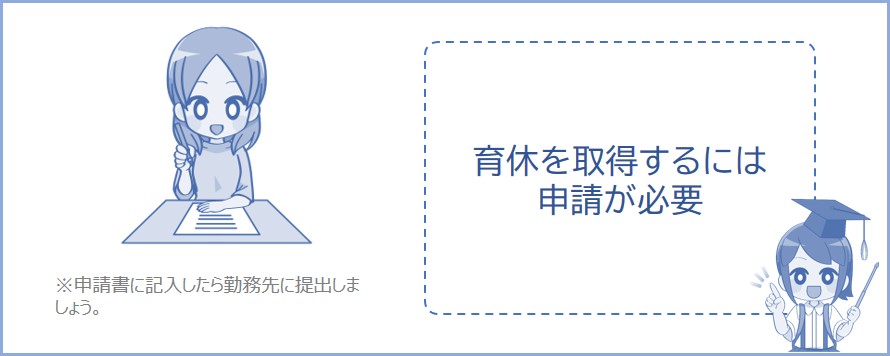
育休は勝手に取得できるわけではありません。
取得する前に勤務先(事業主)に伝えなければいけません。
従業員が育児休業を取得することを伝えると、事業主から「育児休業申出書」を渡されます。
事業主から渡された申請書に休業期間などを記入して提出しましょう。
従業員が育休を取得する際に事業主から「育児休業申出書」を配布されます。
氏名や休業期間などを記入して提出しましょう。
※勤務先に無ければテンプレートをダウンロードしましょう。


記載する内容は?
育児休業申出書には下記の項目などを記入することになります。
- 申出の年月日
- 氏名
- 子の氏名、生年月日、労働者との続柄等(子が出生していない場合は、出産予定者の氏名、出産予定日、労働者との続柄)
- 休業を開始しようとする日
- 休業を終了しようとする日
など。
育休を取得する方は同時に「育児休業給付金」の申請をする場合が多いでしょう。
育休中にもお金が支給されるので、育休を取得するつもりの方は必ずチェックしておきましょう。
下記の記事で申請方法などについて説明しています。また、育休中の手取りがどれくらいになるかシミュレーションもしているのでチェックしておきましょう。
では次に、育休中の社会保険料について下記で説明していきます。育休中は特別な決まりがあります。
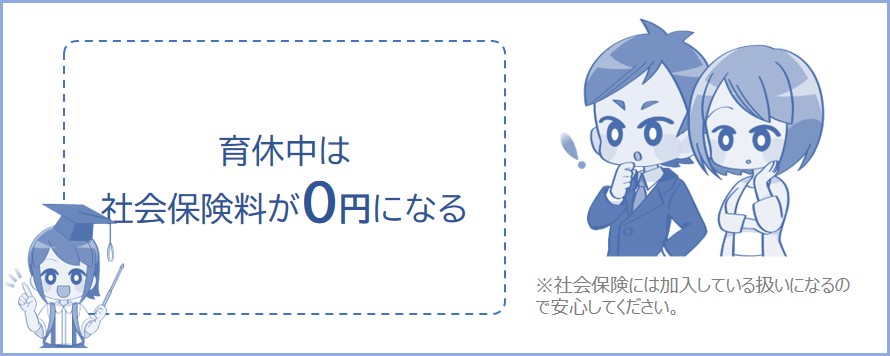
育休を取得した期間は、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が全額免除※されます。
※事業主が申請。事業主・従業員ともに保険料が免除されます。
※今後、自営業やフリーランスの方も保険料(国民年金など)が免除される予定です(2026年度までに)。2025年現在は、まだ免除対象ではありません。
※産前・産後については国民年金も国保も免除・減額されます(本人の申請が必要です)。
つまり、育休を取得した期間の保険料は0円になります。
※ちなみに、厚生年金の保険料が免除されても「保険料を納めた期間」として扱われるので安心してください。
また、免除されているあいだも健康保険は同じように使用することができます。
※たとえば、病気やケガなどの治療費は育休前と同じように3割負担になるので安心してください。
育休を取得すると社会保険料が全額免除されますが、免除されるには条件があります。以下にあてはまるときに免除されます。
免除ポイント1
くわしく説明すると、「育児休業等を開始した日が含まれる月」から「その育児休業等が終了する日の翌日が含まれる月の前月まで」の期間について保険料が免除されます。
例②:たとえば、5月20日に休業開始、5月30日に休業して育休を終了した場合、5月の社会保険料は免除されません。
上記に加えて、「育児休業等開始日が含まれる月」に育児休業等を14日以上取得した場合にも保険料が免除されます。
※賞与(ボーナス)にかかる社会保険料については、賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。
※共済組合や健康保険組合の被保険者の保険料も免除されます。
※参照:日本年金機構従業員が育児休業を取得・延長したときの手続き
※参照:厚生労働省育児・介護休業法のあらまし
では次に、育休中にもらえるお金について下記で説明していきます。育休をする人にとっては大切なお金なので必ずチェックしておきましょう。

育休を取得する方は、休業期間中にお金がもらえる制度「育児休業給付金」について知っておきましょう。
育休中は収入が無くなってしまうので、生活費が不安になる方もいると思います。そんな方のためにあるのが育児休業給付金です。
※育児休業給付金の金額は給料の約67%です(出生後休業支援給付金も上乗せされると最大28日間は約80%になります)。
※育児休業の開始から181日目(6ヶ月)以降は50%になります。
給付金を受けるためには申請が必要なので、育休を取得するときは必ず申請を忘れないようにしましょう。
※くわしくは育児休業給付金とは?手取り金額など解説を参照。

上記でも説明したように、育休中は社会保険料が免除されて0円になります。さらに、育児休業給付金は非課税所得のため、給付金についての税金は0円になります。
したがって、育休中の手取りは休業前の約80%になるんです。
※育休前の手取りが20万円の場合、育休中の手取りは約16万円になります。ただし、育児休業給付金の上限は約30万円となります。
※出生時育児休業給付金も受けるひとは手取りが約100%になります。
子供ができる予定のひとは給付金がどれくらいもらえるか等についてザッと把握しておきましょう。申請方法など下記の記事で説明しています。
育休は会社員やアルバイトにかかわらず、条件にあてはまれば取得することができます。独身の方もこれから子供ができる予定の方も育休について理解しておきましょう。
税金?保険?何もわからない!知っておかなきゃいけないポイントを解説
16歳未満の子供を扶養すると住民税が0円になる?共働きの場合
 しらべたい内容を探す
しらべたい内容を探す
















