被保険者とは?被扶養者とは?第3号被保険者とは?わかりやすく説明
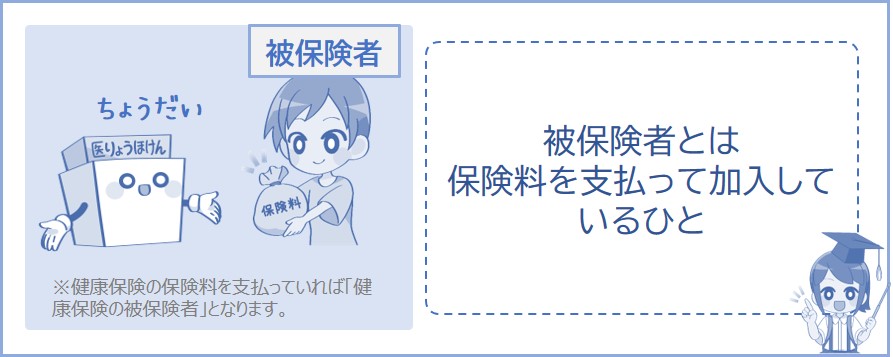
健康保険や介護保険などの保険料をはらって保険に加入している本人を被保険者といいます。
たとえばあなたが勤務先の健康保険に保険料を支払って加入しているなら、あなた本人が健康保険の被保険者となります。
※扶養に入っている方は被扶養者になります(くわしくは下記で解説)。
※介護保険料を払っているなら、介護保険の被保険者になります。
また、国民健康保険の保険料をはらって加入している人は「国民健康保険の被保険者」となります。
したがって、国保に加入しているひとが3人いれば「国保の被保険者は3人」となります(たとえばあなた本人、妻、子供の3人家族)。
※国民健康保険の加入者は、子供でも被保険者となります(国民健康保険には扶養のシステムがないため)。加入者の保険料は世帯主にまとめて請求されます。

保険料をはらって保険に加入しているひとを被保険者といい、その被保険者に扶養されており、被保険者が受ける保険給付(病院代が3割になるなど)を同じように受けられる人を被扶養者といいます。
たとえば「健康保険の被保険者(サラリーマンなど)」に扶養されている子供は健康保険の被扶養者になります。
※あなたが会社員で健康保険の被保険者なら、あなたの子供を被扶養者にすることができます。あなたの親や配偶者(たとえば妻)を被扶養者にすることもできます。
健康保険の被扶養者になれば被保険者と同じように保険給付を受けることができます(病院代などが安くなる等)。
※一部の給付(傷病手当など)は被扶養者は受けられません。
※保険給付については給付の種類を参照。
ちなみに、被扶養者は保険料が0円になるというメリットがあります。したがって、被扶養者として健康保険に加入している子どもなどは保険料を支払う必要がありません。

第3号被保険者※とは、厚生年金の被保険者に扶養されている配偶者のことをいいます。
たとえば夫が厚生年金に加入しており(厚生年金の被保険者であり)、その夫に扶養されている妻は第3号被保険者となります。
※正確には国民年金の第3号被保険者といいます。ちなみに、第1号被保険者は国民年金の被保険者、第2号被保険者は厚生年金の被保険者のことをいいます。
※ただし被保険者(たとえば夫)が65歳以上で、扶養される人(妻)が60歳未満の場合、妻は第3号被保険者には該当しません。
※参考記事→夫が65歳の会社員で妻が50代の場合に気をつけること
第3号被保険者は、自分で支払う国民年金の保険料が0円になります。ただし、第3号被保険者になるには1年間の収入が130万円未満などの条件があります。
※保険料が0円でも国民年金を支払ったことになります。
配偶者の扶養に入ろうと思っている方は覚えておきましょう。
※くわしくは下記の記事で解説しています
社会保険の扶養に入ったときの保険料は0円?
保険や年金に加入すると被保険者・被扶養者・第3号被保険者という用語はかならず関わってくるので、それぞれの意味についてしっかり覚えておきましょう。
漢字だらけで難しそうに感じますが、意味はそれほど難しくありません。
妻が扶養から外れるといくらかかる?夫の税金はいくら増える?
 しらべたい内容を探す
しらべたい内容を探す
















