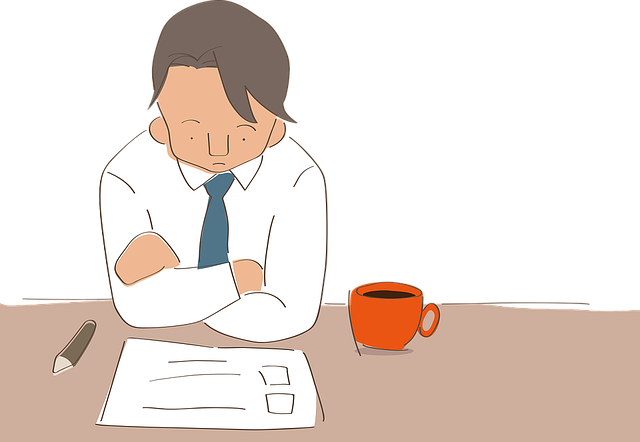退職後の国民健康保険料はいくら?1年目は高い?20万超える?
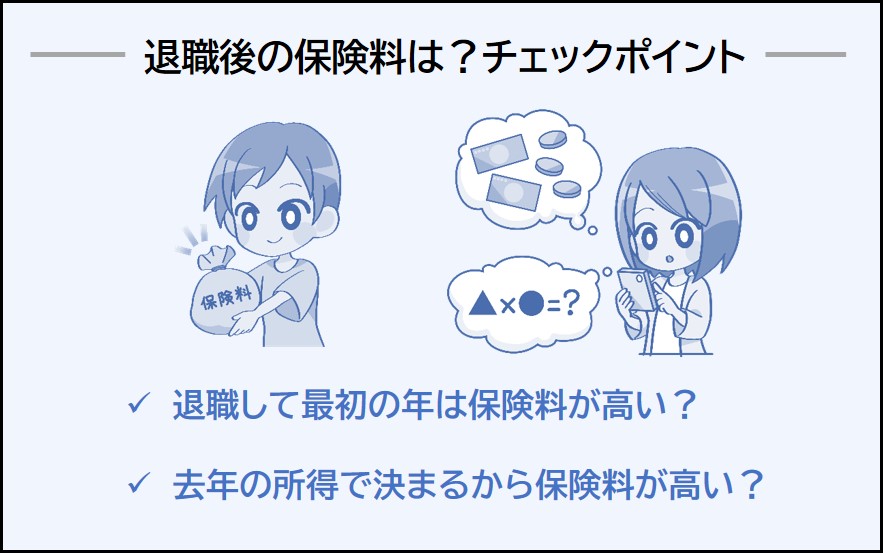
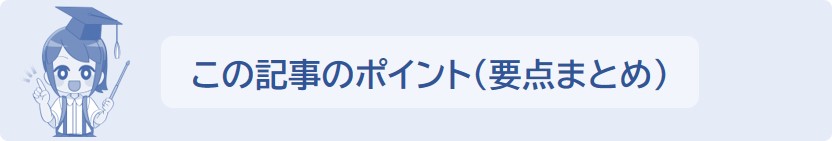
▶退職後の国民健康保険料はいくら?高いの?
国保の保険料は去年1年間(1月~12月まで)の稼ぎで決められる。定年などで、退職して最初の年は保険料が高めになることが多い。退職後の保険料は年間約20万~50万になることが多い。
※社会保険から国民健康保険に切り替えた直後は金額が高くなることがほとんどです。仕事辞めたあとは高額支払いの覚悟をしておきましょう。くわしくは下記で説明しています。
▶退職後、国民健康保険料は安くなるの?
去年1年間(1月~12月まで)の所得が少なければ保険料は安くなる。したがって、退職後2年目から安くなることが多い。
※くわしくは下記で説明しています。
▶任意継続にしたほうが安くなるらしい?
退職前の給料が高かったり、扶養する家族がいる場合、任意継続にしたほうが国民健康保険料よりも安くなることがある。
※くわしくは下記で説明しています。

仕事をやめて今まで加入していた社会保険から抜けたあとは国民健康保険に加入することになります。
※社会保険の扶養に入る場合を除く。
国民健康保険に加入すると保険料を支払うことになるのですが、退職後の収入が0円だとしても初年度の保険料は安くありません。
※加入月の翌月から保険料を支払うことになります。
※4月に国民健康保険に加入手続きをした場合は、6月中旬に納付書が送付されます(4月から翌年3月までの1年分)。お住まいの地域によっては7月や8月など時期が異なる場合もあります。
なぜかというと、今年度(4月から翌年3月まで)の保険料は去年の所得によって決定するためです。したがって、現在収入が無くても退職後1年目の保険料は安くないんです。

国民健康保険の保険料は前年1月~12月までの所得によって決まります。
したがって、去年1月~12月に会社員やアルバイトなどをしてお金を稼いでいれば今年の保険料はそれなりの金額になります。
ちなみに、40歳以上~64歳・独身・東京都世田谷区に住んでいる方が4月に国民健康保険に加入した場合、前年1月~12月までの給料(総支給額)が400万円だとすると、今年度の保険料は約375,000円になります。
※1年分の保険料は送付された納付書を用いて数回~10回に分けて支払うことになります。再就職して社会保険に加入した場合、社保に加入した月の前月まで国民健康保険料を支払うことになります(余計に払ったぶんは返金されます)。
※ちなみに、上記の条件のひとで 前年の所得が0円だとすると1年間の保険料は約25,000円になります(7割減額されるため)。
無職になって支払うお金についてはこちら↓
無職になったら毎月かかるお金は?
では次に、退職後の保険料がいくらになるか金額をあてはめてシミュレーションして説明していきます。
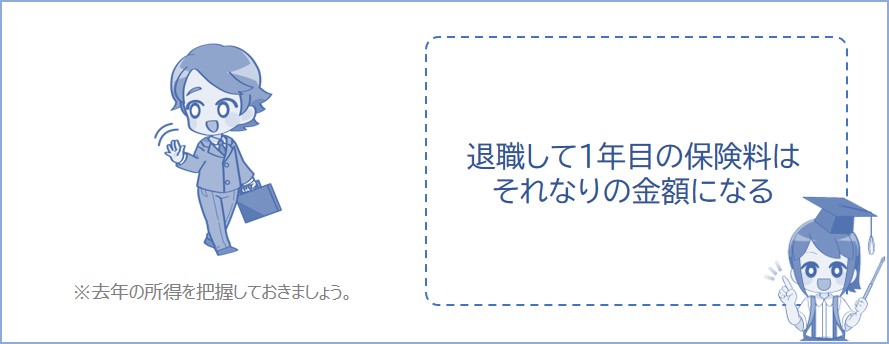
国民健康保険料は前年1月~12月の所得をもとに今年度の保険料(今年4月~翌年3月まで)が計算されます。
以下に①退職した初年度の保険料、②退職した翌年度の保険料、③退職した翌々年度の保険料をシミュレーションしました。
※退職1年目、2年目、3年目の保険料がいくらになるか大まかに把握しておきましょう。
退職後に社会保険から国民健康保険に切り替える予定の会社員などはチェックしておきましょう。
※60歳以上になって定年で退職する方も保険料をザッと計算できるようにしておきましょう。
※60歳~65才以上の年金受給者の国民健康保険料はこちらの記事で解説。定年後の保険料をザッと把握しておきましょう。
今年3月31日に退職した場合、国保の加入資格は4月1日からとなるので今年4月~翌年3月までの国民健康保険料を支払うことになります。
※1年分の保険料は送付された納付書を用いて数回~10回に分けて支払うことになります。
たとえば去年1月~12月までの給与収入が500万円だったとすると、今年4月~翌年3月までの国民健康保険料は約47.7万円となります。今年4月から加入したとすると、保険料は
※世田谷区・独身・40歳以上~64歳の会社員として計算。
※国民健康保険料のシミュレーションはこちらで行えます。保険料率はお住まいの地域によって異なります。
となります。
※再就職して社会保険に加入した場合、社保に加入した月の前月まで国民健康保険料を支払うことになります。
※再就職までかかる税金や保険料などは退職後のお金シミュレーションで計算できます。
※翌年4月~翌々年3月までが1年度の国民健康保険料になります。
今年3月31日に退職しており、4月からは収入0円なので、今年1月~12月までの給与収入が130万円だったとすると、翌年4月~翌々年3月までの国民健康保険料は約12.1万円となります(2割減額※1された場合は年間約105,000円)。
※1 減額については下記で説明しています。
※世田谷区・独身・40歳以上~64歳の会社員として計算。
※国民健康保険料のシミュレーションはこちらで行えます。保険料率はお住まいの地域によって異なります。
※翌々年4月~翌々々年3月までが1年度の国民健康保険料になります。
今年3月31日に退職しており、翌年1月~12月までの収入が無職で0円だったとすると、翌々年4月~翌々々年3月までの国民健康保険料は約81,000円(7割減額※1された場合は年間約24,000円)となります。
※1 減額については下記で説明しています。
※世田谷区・独身・40歳以上~64歳として計算。
※年収ごとの保険料は下記表にまとめています。
こんなページもみられています
60~65才以上の年金受給者の国民健康保険料はいくら?

国民健康保険料は前年1月~12月の所得をもとに今年度の保険料(今年4月~翌年3月まで)が計算されます。
年度の途中で退職した場合は、加入した月から保険料が計算されます。
以下に①退職した初年度の保険料、②退職した翌年度の保険料、③退職した翌々年度の保険料をシミュレーションしました。
※いつから国保の保険料を支払うことになるかチェックしておきましょう。
たとえば今年9月25日に退職した場合、国保の加入資格は9月から※となるので今年9月~翌年3月までの7カ月分の国民健康保険料を支払うことになります。
※国保は退職した翌日が加入月となります。
※保険料は送付された納付書を用いて数回に分けて支払うことになります。
たとえば去年1月~12月までの給与収入が500万円だったとすると、今年4月~翌年3月までの国民健康保険料は約47.7万円となります。今年9月から加入したとすると、保険料は約27.8万円となります。
※再就職して社会保険に加入した場合、社保に加入した月の前月まで国民健康保険料を支払うことになります。
※再就職までかかる税金や保険料などは退職後のお金シミュレーションで計算できます。
※翌年4月~翌々年3月までが1年度の国民健康保険料になります。
今年9月25日に退職しており、10月からは収入0円なので、今年1月~12月までの給与収入が375万円だったとすると、翌年4月~翌々年3月までの国民健康保険料は約35万円となります。
※世田谷区・独身・40歳以上~64歳の会社員として計算。
※保険料はこちらのページでシミュレーションできます。
※翌々年4月~翌々々年3月までが1年度の国民健康保険料になります。
今年9月25日に退職しており、翌年1月~12月までの収入が無職で0円だったとすると、翌々年4月~翌々々年3月までの国民健康保険料は約81,000円(7割減額※1された場合は年間約24,000円)となります。
※1 減額については下記で説明しています。
※世田谷区・独身・40歳以上~64歳として計算。
こんなページもみられています
60~65才以上の年金受給者の国民健康保険料はいくら?
では次に、退職後の1年間の保険料について下記で説明していきます。年収ごとにまとめています。
※仕事を辞めた直後にどれくらいお金を残しておけばいいのか把握しておきましょう。
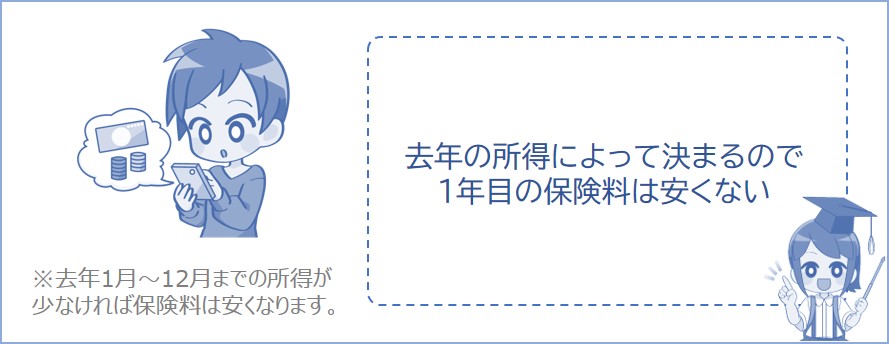
退職したあとに国民健康保険に加入した場合の保険料をシミュレーションしました。
退職前にお金を稼いでいた場合、退職1年目の保険料は下記のようにそれなりの金額になることを覚えておきましょう。
※保険料は去年1年間の所得によって決まるため。
※退職2年目・3年目については上記でシミュレーションしています。
ちなみに、下記のシミュレーションは1年間(4月から翌年3月まで)の保険料になっています。
※1年間の保険料は数回~10回に分けて納付することになります。
※再就職などで途中で国保を抜けたら資格喪失した月の前月までの保険料を支払うことになります。
| 去年1月~12月までの年収 | 1年間の国保の保険料 ※3月末で退職した場合 |
|---|---|
| 300万円 | 約229,000円 ※ひと月あたり約19,000円。 ※40~64歳の場合は約28.2万円 |
| 350万円 | 約266,000円 ※ひと月あたり約22,000円。 ※40~64歳の場合は約32.6万円 |
| 400万円 | 約306,000円 ※ひと月あたり約26,000円。 ※40~64歳の場合は約37.5万円 |
| 450万円 | 約348,000円 ※ひと月あたり約31,600円。 ※40~64歳の場合は約42.6万円 |
| 500万円 | 約390,000円 ※ひと月あたり約33,000円。 ※40~64歳の場合は約47.7万円 |
| 550万円 | 約431,000円 ※ひと月あたり約35,900円。 ※40~64歳の場合は約52.7万円 |
| 600万円 | 約473,000円 ※ひと月あたり約39,400円。 ※40~64歳の場合は約57.8万円 |
※市区町村によって保険料は異なります。
※3月末に退職してから1年間(4月から翌年3月まで)の保険料です。
※給与収入・世田谷区・加入者1人として計算(ほかに加入者がいれば保険料は増えます)。
※保険料は国民健康保険シミュレーションで計算。
※退職2年目・3年目については上記でシミュレーションしています。
※退職後に毎月かかるお金は無職になったら毎月かかるお金は?を参照。
では次に、任意継続にしたほうが安くなるのかについて下記で説明していきます。人によって違うのでシミュレーションしてみましょう。
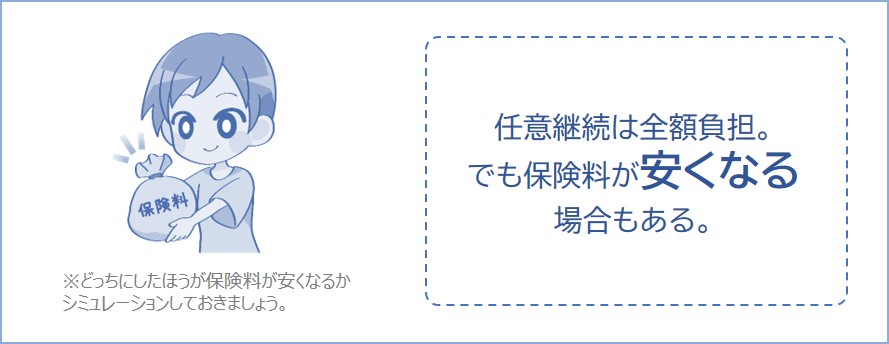
退職後は健康保険をぬけて国民健康保険に加入することになります。
※親族の健康保険の扶養に入る場合は除く。
ですが、本人が希望すれば退職したあとも勤務先の健康保険に加入することができます。これを健康保険の任意継続といいます。
※任意継続は保険料を期限までに納付することによって個人の希望で加入期間を継続する制度です。
任意継続をすると、全額負担になるので保険料が高くなる傾向があります。
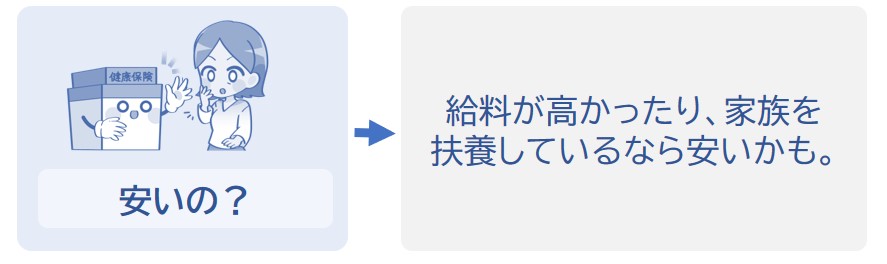
ひとによっては任意継続にしたほうがメリットがあります。保険料が安くなったり、加入している保険組合によっては「ほかの公的保険よりも病院代が安くなる」などの給付を退職後も引き続き受けることができます。
たとえば退職前の給料が高かったひとや扶養する親族が多くいる場合は 任意継続にしたほうが安くなることが多いです。
※退職する前にどっちが安くなるか比較して任意継続にするか国民健康保険に加入するか選択しましょう。下記の記事で保険料をシミュレーションしているので気になる方はチェックしておきましょう。


国民健康保険は世帯の所得が少なければ保険料が減額されます。前年(1月~12月まで)の所得によって7割~2割減額されます。
したがって、3月末に退職してから収入が0円の場合は 2年目から保険料が減額される可能性が高いです。
たとえば無職で今年の収入が0円(所得が無い)なら、翌年度の年間保険料は7割減額されます。
※世帯主または本人以外の被保険者がたくさんお金を稼いでいる場合は減額されない場合があります。
前年の所得に応じて7割~2割減額されると、1年間の保険料が48,000円なら14,400円~38,400円になるということです。くわしくは下記の記事で説明しているのでチェックしておきましょう。
倒産や解雇などの会社都合等でやむをえず退職したひとは保険料が減額されます。
※65歳未満のひとに限ります。
雇用保険受給資格者証をハローワークで発行してもらい、お住まいの市区町村役所で申請をすることになります。
※雇用保険受給資格者証はハローワークにて離職票を提出し、求職の申し込みをしたのち(約1週間後)に開催される雇用保険受給者初回説明会で配布されます。
減額してくれる期間は離職日の翌日の属する月から、翌年度3月末までなのでお早めに申請しましょう。
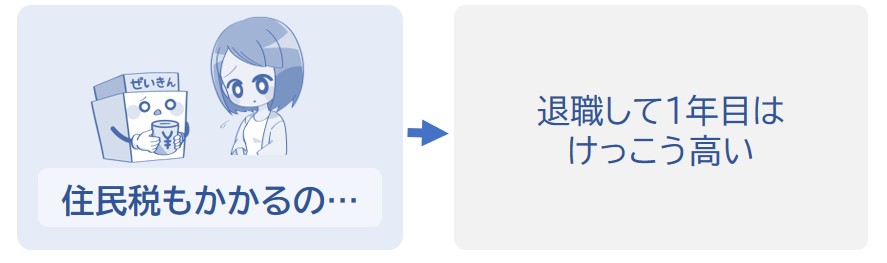
上記では保険料について説明しましたが、退職後1年目の住民税もそれなりの金額になることが多いです。
したがって、退職するつもりの会社員などは退職後の住民税の支払いにも注意しておきましょう。
ある程度まとまったお金を用意しておくことをオススメします。退職してから貯金をすべて使ってしまって「保険料や住民税が支払えない…」とならないように気をつけましょう。
くわしくは下記の記事で説明しています。
退職後、無職でも住民税は高い?安くなるのは2年目から?
▶退職して収入0円だと国民健康保険はいくら?
退職後、収入が0円でも初年度の保険料はそれなりの金額になる。
※くわしくは上記で説明しています。
▶保険料は安くなるの?
1年間の所得が少ないと保険料が最大7割減額される。
※くわしくは上記で説明しています。
▶健康保険を任意継続したほうがいいの?
任意継続は全額負担になるが、退職前の給料などによっては任意継続のほうが保険料が安くなる場合もある。
※くわしくは上記で説明しています。
こんなページもみられています
任意継続とは?メリットは?国保とどっちが高いか比較
60~65才以上の年金受給者の国民健康保険料はいくら?
 しらべたい内容を探す
しらべたい内容を探す