任意継続とは?メリットは?国保とどっちが高いか2つを比較シミュレーション
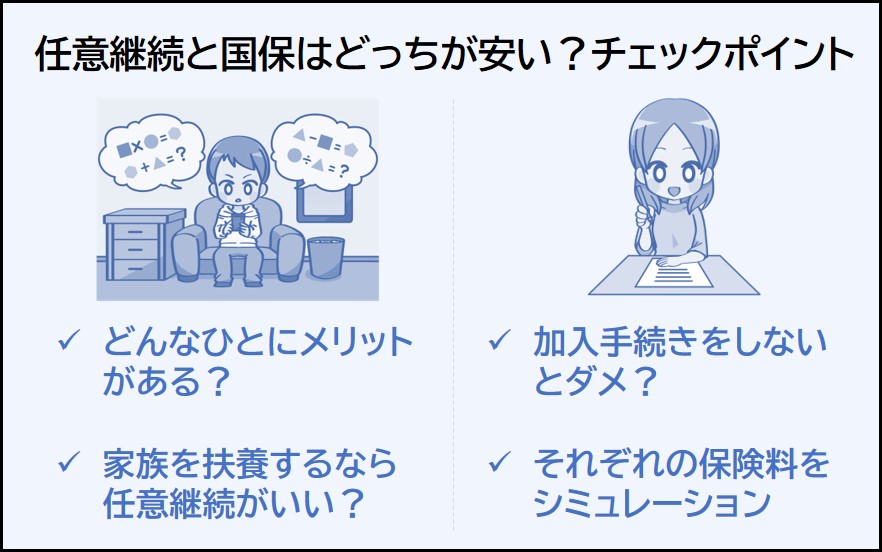
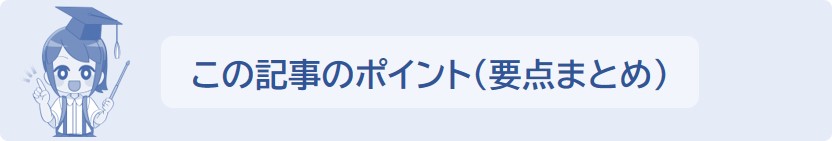
▶任意継続にした方がいい人は?
扶養する家族がいる場合や退職前の給料が多かった場合は任意継続のほうが安くなることが多いのでメリットがある。
※くわしくは下記で説明しています。
▶任意継続のメリットは?
・会社独自の給付を受けられることがある。
※くわしくは下記で説明しています。
▶退職後は国保と任意継続のどちらが保険料安い?
任意継続の保険料は全額負担なので高くなることが多い。月収30万円だった場合で国民健康保険とシミュレーションすると国保のほうが安い傾向がある。
※任意継続が月額約3万、国保が月額約2.5万となり、国保のほうが安くなります(ただし、保険料は組合や市区町村によって異なります)。くわしくは下記で説明しています。
▶任意継続のほうが安くなるときは?
保険組合に上限があったり、扶養する家族がいる場合は国民健康保険よりも保険料が安くなることが多い(国保には扶養のシステムが無いため)。
※たとえば年収300万なら国保のほうが安くなる傾向ですが、扶養する家族がいる場合は任意継続のほうが安くなることもあるので比較してみましょう。
※上限については下記で説明しています。
※扶養についてはほかにも注意することは?で解説。
では、任意継続とはなんのことなのかについて下記で説明していきます。健康保険を任意継続するひとはチェックしておきましょう。
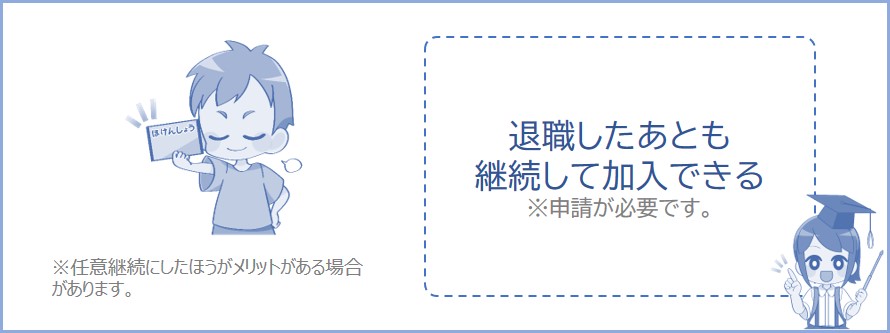
本人が希望すれば退職をしたあとも勤務先の健康保険に一定期間加入することができます。これを健康保険の任意継続といいます。
※無職になっても任意継続として健康保険に加入することができます。
※任意継続は保険料を期限までに納付することによって個人の希望で加入期間を継続する制度です(共済組合にも任意継続があります)。
たとえば勤務先の保険組合に「ほかの公的保険よりも病院代が安くなる」などのメリットがある場合、任意継続をすれば退職した後もそのメリットを受けることができます。
※任意継続をしなければ退職後に勤務先の保険組合を抜けなければいけないので、保険組合の給付を受けることはできません。
※加入している保険組合によっては一部受けられない給付もあります。自社のHPで確認しておきましょう。
上限があったり、扶養する家族がいる場合は退職後に任意継続を選択したほうが国民健康保険料よりも安くなるときが多いです。なので、保険料が気になる方は退職前にシミュレーションすることをおすすめします。
※どっちの保険料が安いのか比較シミュレーションは下記の項目で説明しています。
では次に、任意継続にするメリットについて下記で説明していきます。任意継続にすると保険料が安くなるときがあります。
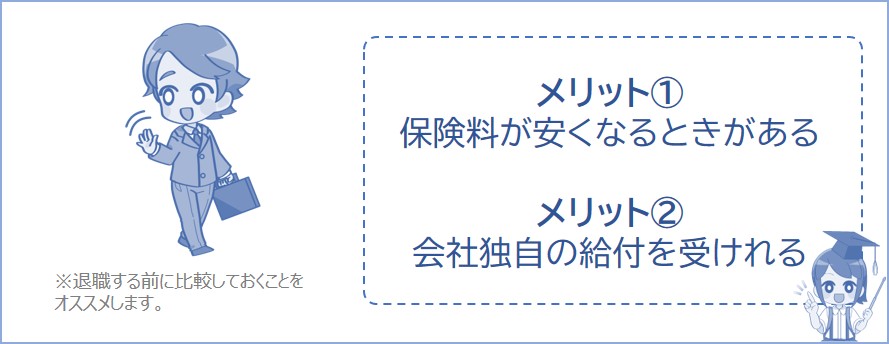
任意継続は保険料が全額負担になるので、退職前よりも保険料金が高くなる傾向があります。
ただし、退職前に給料をたくさんもらっていた人は、場合によっては保険料が安くなることがあります。この場合、任意継続にしたほうがメリットがあるといえるでしょう。
※くわしくは下記の任意継続の保険料には上限がある?で説明しています。
また、扶養する家族がたくさんいる場合、国民健康保険よりも保険料が安くなることがあります。この場合、任意継続にしたほうがメリットがあるといえるでしょう。
※下記のほかにも注意することは?で説明しています。
保険料だけでなく、加入している保険組合によっては国民健康保険よりも「病院代の負担が少なくて済む」等の給付を受けられる場合があります。したがって、会社の保険組合の独自給付を利用するつもりの方は任意継続にしたほうがメリットがあるといえるでしょう。
※任意継続をする前に加入している保険組合の給付や保険料についてしっかり調べておくことをオススメします。
こんなページもみられています
任意継続の保険料をパッと計算シミュレーション
では次に、任意継続と国民健康保険の保険料の比較について下記で説明していきます。どっちのほうが保険料が安くなるのかシミュレーションしてみましょう。
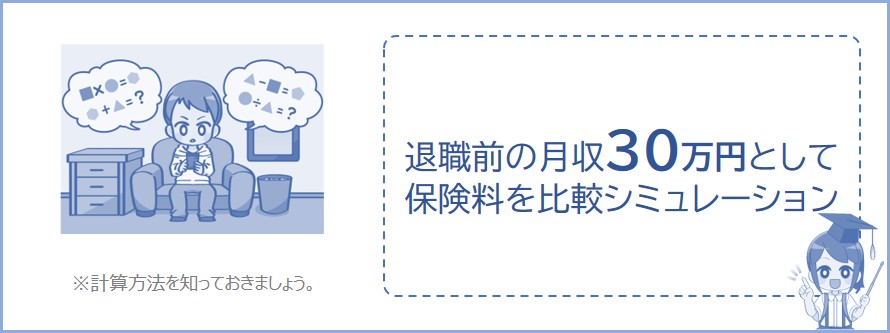
健康保険の保険料は会社と折半しているので、会社に勤めていたときの保険料は半分の負担で済んでいます。
しかし、任意継続になると保険料は全額負担になります。なので、以前より保険料は高くなる傾向があります。
※ただし、退職前の給料が高額だったひとは任意継続にしたほうが安くなる場合もあります。くわしくは下記の項目(任意継続には上限がある?)で説明しています。
以下は月収が30万円(年収360万円)だった場合の保険料シミュレーションです。退職予定の会社員やアルバイトなどの方はチェックしておきましょう。
※任意継続をする前に国民健康保険の保険料としっかり比べましょう。
たとえば月収30万円(年収360万円)を稼いでいたひとの任意継続の保険料は以下のようになります。
※厳密には356,760円。
※保険料率は協会けんぽの数値(40歳未満,東京都)で計算しています。
※任意継続は全額負担なので半額にはなりません。
※月収30万円の標準報酬月額は30万円になります。
※任意継続の保険料はこちらのシミュレーションで計算できます。
次に国民健康保険の保険料を計算してみましょう。
退職前の1年間(去年1月~12月まで)の給料が360万円だとすると、国民健康保険料は以下のようになります。
給料が360万円なので給与所得は以下のようになります。
※給与所得は給与所得シミュレーションで計算できます。
給与所得のほかに所得は無いので、244万円が総所得金額等になります。
②次に所得割を計算
総所得金額等が244万円なので、所得割は以下のようになります。
(
※43万円は基礎控除として一律に引かれます。
※所得割については所得割とはを参照。
③次に国民健康保険料を計算
国民健康保険料は所得割と均等割の合計なので、1年間の保険料は以下のようになります。
※世田谷区、40歳未満独身の場合は273,000円となります。
※所得割・均等割については所得割・均等割とはを参照。
※100円未満は切り捨てして計算する場合もあります。
※保険料の計算方法は国民健康保険とはを参照。
※保険料率等は市区町村によって異なります。
国民健康保険料は以下のページで計算できます。

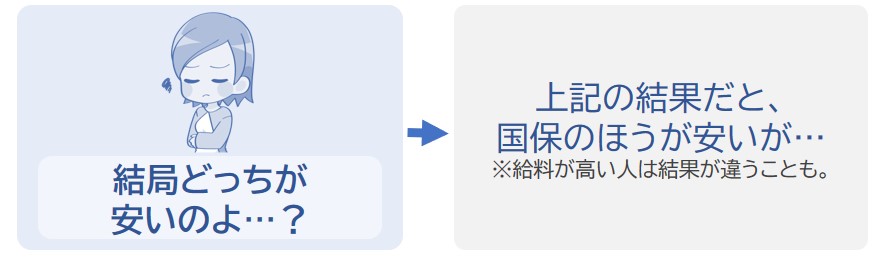
上記で比較シミュレーションした場合※、年収360万(月収30万)のとき任意継続が約36.0万円(月額約3万)、国保が約27.3万円(月額約2.3万)なので、任意継続よりも国民健康保険のほうが保険料が安くなります。
※世田谷区・40歳未満・独身・年収360万円の場合。
ただし、退職前に給料をたくさんもらっていた方は任意継続に上限ができる場合があります。この場合、任意継続にしたほうが保険料が安くなります。
※くわしくは次の項目で説明していきます。
では次に、任意継続のほうが安くなる場合について下記で説明していきます。任意継続には上限が決められている場合があります。
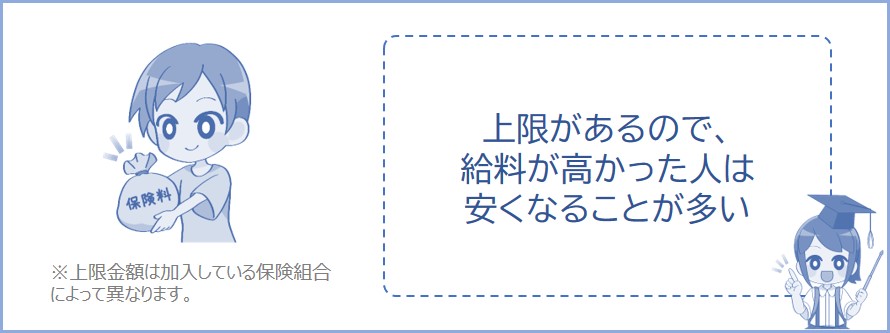
任意継続になると保険料は全額負担になるので、以前より高くなる傾向があります。
ただし、場合によっては保険料が安くなることもあります。なぜかというと、任意継続の保険料には上限が設定されている場合があるからです。
高額な給料をもらっていたひとはそれだけ保険料も高くなりますが、退職後に任意継続にすることで以前より安くなる場合があるんです(保険料に上限ができるため)。
わかりやすく説明するために以下でシミュレーションしていきます。
※下記の場合、月収80万のとき任意継続が約38.0万円(月額約3.2万)、国保が約81万円(月額約6.8万)なので、任意継続のほうが保険料が安くなります。
※世田谷区・40歳未満・独身・年収960万円の場合。
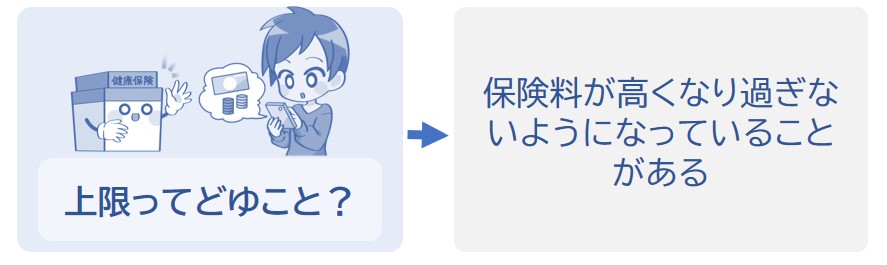
たとえば月収80万円を稼いでいたひとの退職前の保険料は以下のようになります。
※月収80万円だと標準報酬月額は79万円になります。
※保険料率は協会けんぽの数値(40歳未満,東京都)で計算しています。
※半額分は事業主が支払うので÷2をして計算しています。
※このとき、任意継続に加入すれば全額負担になるので約78,000円(月額の保険料)になります(上限が無い場合)。
ですが、任意継続の保険料には上限が設定されている場合があります※。上限を32万円とすると、退職前の月収が80万円だとしても保険料は以下のようになります。
※厳密には標準報酬月額に上限が設定されている。
※下記で説明するように、加入している保険組合によっては上限が無い場合があります。
※厳密には31,712円
※保険料率は協会けんぽの数値(40歳未満,東京都)で計算。
※任意継続は全額負担なので半額(÷2)にはなりません。
※協会けんぽの任意継続は標準報酬月額32万円が上限(以前は30万でした)。
※ちなみに、世田谷区40歳未満で月収80万円(年収960万円)のとき、国民健康保険料は約81万円(月額68,000円)になります。
以上のように、退職前に高額な給料をもらっているひとは任意継続のほうが保険料が安くなる場合があります。ただし、加入している保険組合によって標準報酬月額の上限は異なるので保険料がもっと高額になることがあります。
※自分の保険組合についてしっかりチェックしておきましょう。
※参照:厚生労働省全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律pdf
任意継続の計算はこちら
任意継続の保険料をパッと計算シミュレーション
では次に、任意継続と国保の2つの保険料をくらべた金額について下記で説明していきます。表にまとめて見やすくしています。
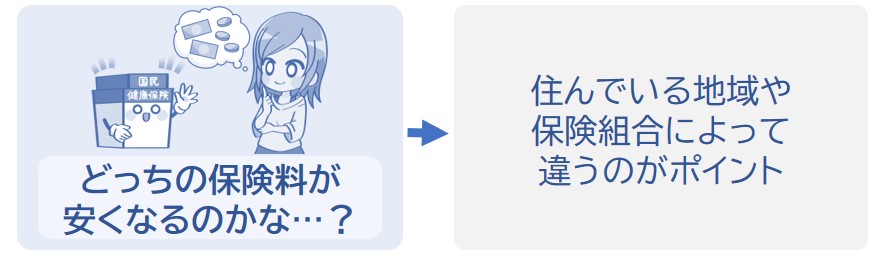
下記は3月末に退職した会社員として計算しています。
下記は「協会けんぽ」でシミュレーションしています。
※加入している保険組合によっては上限が無いことがあります(協会けんぽだと下記のように上限が設けられています)。
※上限については上記で説明しています。
※それぞれ保険料の計算方法は上記を参照。
| 年収 | 国民健康保険 | 任意継続 |
|---|---|---|
| 250万 | 1年間の保険料は 約19.3万円 ※ひと月当たり約1.6万円 |
1年間の保険料は 約23.8万円 ※ひと月当たり約2.0万円 |
| 300万 | 1年間の保険料は 約22.9万円 ※ひと月当たり約1.9万円 |
1年間の保険料は 約30.9万円 ※ひと月当たり約2.6万円 |
| 360万 | 1年間の保険料は 約27.3万円 ※ひと月当たり約2.3万円 |
1年間の保険料は 約35.7万円 ※ひと月当たり約3.0万円 |
| 400万 | 1年間の保険料は 約30.6万円 ※ひと月当たり約2.5万円 |
1年間の保険料は 約38.0万円 ※ひと月当たり約3.2万円 |
| 500万 | 1年間の保険料は 約39.0万円 ※ひと月当たり約3.3万円 |
1年間の保険料は 約38.0万円 ※ひと月当たり約3.2万円 |
|---|---|---|
| 700万 | 1年間の保険料は 約56.0万円 ※ひと月当たり約4.7万円 |
1年間の保険料は 約38.0万円 ※ひと月当たり約3.2万円 |
※世田谷区、40歳未満、独身として計算。
※任意継続は保険組合によって金額が変わります。
※国保は市区町村によって金額が変わります。
※任意継続は任意継続シミュレーションで計算。
※国保は国民健康保険シミュレーションで計算。
保険料の上限を調べるには、自分が加入している保険組合のHPを見て確認しましょう。上記とは金額が変わることがあります。
※加入している保険組合によっては上限が無い場合があります(上記表では任意継続の金額の上限が38万になっています)。
また、家族を扶養している人数によっては国保の保険料が増えるので、任意継続にしたほうがお得な場合があります。
※くわしくは下記で説明していきます。
では次に、任意継続と国民健康保険をくらべるときの注意ポイントについて下記で説明していきます。扶養や減額がキーポイントです。
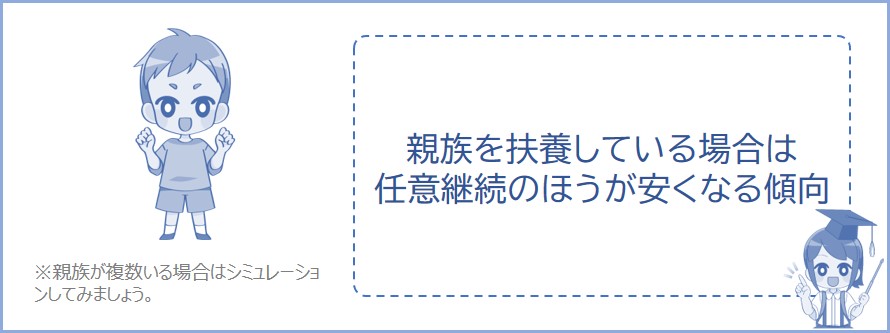
任意継続と国民健康保険の保険料を比較しましたが、ほかにも注意することがあります。
注意点は「国保の保険料が減額されること」、「国保には扶養のシステムがないこと」です。
とくに扶養する家族がいる方はチェックしておきましょう。
国民健康保険は前年(1月~12月まで)の世帯所得が少なければ保険料が最大7割減額されます。したがって、退職後最初の1年間は任意継続のほうが安くても2年目からは国民健康保険のほうが安くなる場合があります。
※くわしくは以下のページで説明しています。
退職後の国民健康保険料はいくら?1年目は高い?
無職の場合の国民健康保険料はどれくらい?所得が少ないと安くなる?
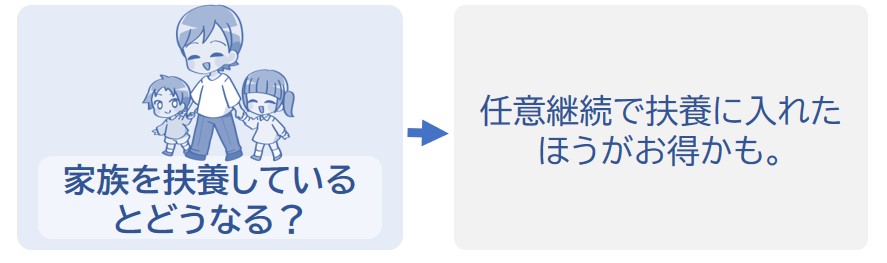
たとえば扶養に入れることができる親族がたくさんいる場合、任意継続を選択して親族を扶養にいれたほうが国民健康保険の保険料よりも安くなる場合があります。
国民健康保険には扶養のシステムがないので子供などがたくさんいる場合はそのぶん保険料が加算されてしまいます。
※国民健康保険は加入者ごとに保険料がかかるので、お金を稼いでいない子供でも国保に加入すれば保険料が加算されるシステムになっています。
ただし、お金を稼いでいない加入者についての国民健康保険料は均等割のみになります。均等割は1人あたり年間約4万円~8万円の場合が多いです(市区町村によって異なる)。
※つまり、子供が3人いれば保険料が年間約12万円~24万円加算されることになります(未就学児の均等割は5割減額されます)。くわしくは国民健康保険料シミュレーションで計算できます。
※任意継続は任意継続シミュレーションで計算。
以上のことから、家族がたくさんいる場合は任意継続を選択したほうが保険料が安くなる場合があります。
では次に、任意継続をするための条件や手続きについて下記で説明していきます。任意継続をするときは手続きが必要です。
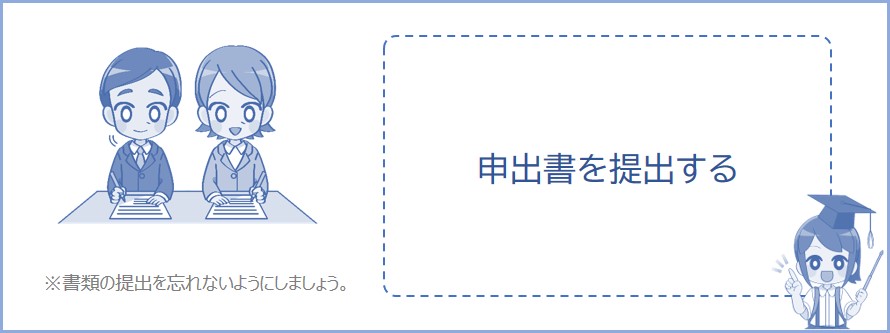
任意継続をするには以下の2つを満たさなければいけません。
任意継続をするつもりの方は早めに準備しましょう。
- 退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること
- 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出(必着)すること
※20日目が土日・祝日の場合は翌営業日が期限になります。
※こんなページもみられています
再就職するまでの空白期間は国保に加入したほうがいい?
では次に、任意継続の加入期間について下記で説明していきます。また、資格を喪失する(任意継続を抜ける)条件についても説明していきます
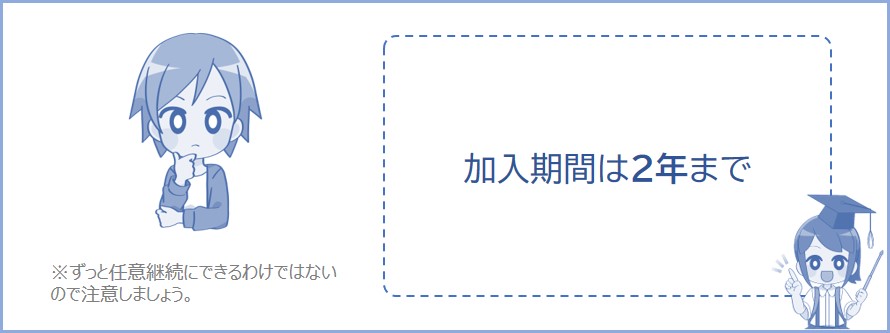
任意継続の加入期間は2年間(退職日の翌日に資格を取得してから2年間)です。
ただし、以下の1~6のいずれかにあてはまる方は2年の加入期間中であっても任意継続の資格を喪失することになります。
※2022年1月の改正により、自己都合で任意継続をやめる(資格を喪失する)ことができるようになりました。
※3~5の理由で資格を喪失するときは資格喪失申出書を提出することになります。
※くわしくは加入している保険組合で確認することをオススメします。
※参照:全国健康保険協会任意継続とは
以上の条件①~⑥のどれかを満たしたときに任意継続の資格を喪失することになるので覚えておきましょう。
任意継続の加入期間中に「期限までに保険料を支払わなかった」場合は任意継続の資格を喪失(脱退)することになります。
※任意継続は保険料を期限までに納付することによって個人の希望で加入期間を継続する制度です。
※資格喪失の条件にあてはまるので任意継続の資格を喪失することになります。
※ちなみに、任意継続の保険料は加入した期間が1日だとしてもひと月分かかります。くわしくは再就職するまでの空白期間は国保に加入したほうがいい?を参照。
では次に、届出の提出について下記で説明していきます。扶養に入れる親族を変更するときなどに届出を提出することになります。
任意継続を選択して親族を扶養に入れる場合は届出を提出して申請しなければいけません。何もしないと親族は扶養に入れることができないので注意しましょう。
また、再就職などで任意継続の資格を喪失するときには申請書を提出して保険証も返却しましょう。そのままにしていると保険料が請求されてしまうので早めに手続きをしましょう。
※申請書は加入している保険組合HPにてダウンロードしましょう。
任意継続の保険料をパッと計算シミュレーション
国民健康保険の保険料をパッと計算シミュレーション
年収100万~600万の国民健康保険料はいくら?家族1人~5人だと?
無職になったら毎月かかるお金は?退職後3か月休むと税金はいくら?
 しらべたい内容を探す
しらべたい内容を探す
















