特定親族特別控除とは?年収188万以下の子供がいれば税金が安くなる?

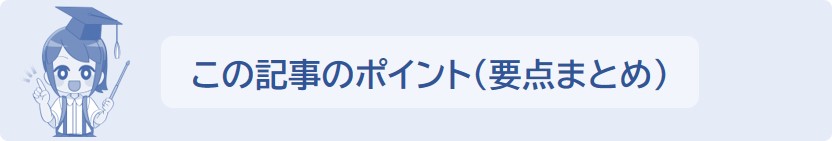
▶特定親族特別控除でどれくらい税金が安くなるの?
特定親族特別控除を利用すると税金が約0.5万円~17万円安くなる。子供の所得によって安くなる金額が変わるのがポイント。
※くわしくは下記で説明しています。年収によってどれくらい変わるかチェックしておきましょう。
▶23歳の子供は特定親族特別控除は利用できる?
特定親族特別控除は18歳以下や23歳以上だと対象外。12月31日時点の年齢で19歳~22歳であることが条件。
※くわしくは下記で説明しています。
▶控除は自動的に適用されるの?
大学生は150万まで稼いでも扶養を外れない?

たとえば「扶養親族の対象から外れてしまった子供」でも特定親族であれば特定親族特別控除が適用されます。
子供がアルバイトをしており、その給与が年収123万(合計所得58万)を超えてしまうと扶養親族の対象外になってしまいますが、19歳以上~23歳未満の子供なら年収123万超~188万以下であれば「特定親族の対象」となり、特定親族特別控除を利用することができます。
※最大63万円(最小3万円)の控除が適用されます。
くわしい金額は以下の表のようになっています。
▶特定親族特別控除の控除額の表


※子供のバイト収入150万までは扶養控除と控除額が変わりません(63万円)。
※参照:国税庁令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

上記の表を見てわかるように、19歳~22歳の子供の合計所得が95万円(給料のみで年収160万)を超えると控除額が51万円になり、MAXから12万円減ります。したがって、親の税金が安くなる効果が減ります。
※この場合、親の税金がどれくらい増えるのかについては下記でシミュレーションしています。
給与所得控除については給与所得控除とは?を参照。
給与所得については給与所得シミュレーションで計算できます。
※2025年の改正により、給与所得控除の最低保証額が10万円引き上げされました。
給与収入160万だと合計所得95万なので、上記表と照らしあわせると控除額は51万になります。
では次に、特定親族特別控除を利用するとどれくらい税金が安くなるのかについて下記で説明していきます。

年収にもよりますが、特定親族特別控除を利用すると税金は年間約0.5万~17万円ほど安くなることが多いでしょう。
※所得税と住民税が安くなります。
※これから初めて控除を受ける会社員などは約0.5万~17万円の税金が安くなることになります。
税金がいくら戻るのか気になる方は下記のシミュレーションをチェックしておきましょう。
※住民税は翌年度の金額に反映されます(住民税は前年の所得で決定するため)。
※住民税は6月~翌年5月までが1年度の金額になります。
150万以下なら安くなる金額はMAX?
子供の収入がアルバイト収入のみであり、年収150万以下(つまり合計所得85万以下)であれば控除額はMAX(63万円)なので、安くなる税金額もMAXになります。
※合計所得85万を超えると安くなる金額はMAXから少しずつ下がっていきます。
※控除額MAX(63万円)については上記表を参照。
たとえば40歳以下・社会保険加入・特定親族1人という条件の方が控除を利用したとき。
※合計所得58万超えからは特定親族の対象(58万以下なら扶養親族の対象)。
| 子供の合計所得 | 親の年収300~400万円のとき | 親の年収570~640万円のとき | 親の年収760~850万円のとき |
|---|---|---|---|
| 58万円以下 ※給料なら年収123万円以下 |
税金は約77,000円安くなります。 所得税32,000円 住民税45,000円 |
税金は約108,000円安くなります。 所得税63,000円 住民税45,000円 |
税金は約171,000円安くなります。 所得税126,000円 住民税45,000円 |
※↑合計所得58万以下までは扶養控除。
↓ここから↓58万超からは特定親族特別控除。
| 58万超~85万円以下 ※給料なら年収150万円以下 |
税金は約77,000円安くなります。 所得税32,000円 住民税45,000円 |
税金は約108,000円安くなります。 所得税63,000円 住民税45,000円 |
税金は約171,000円安くなります。 所得税126,000円 住民税45,000円 |
|---|---|---|---|
| 90万円以下 ※給料なら年収155万円以下 |
税金は約72,000円安くなります。 所得税31,000円 住民税41,000円 |
税金は約101,000円安くなります。 所得税60,000円 住民税41,000円 |
税金は約163,000円安くなります。 所得税122,000円 住民税41,000円 |
| 95万円以下 ※給料なら年収160万円以下 |
税金は約68,000円安くなります。 所得税27,000円 住民税41,000円 |
税金は約92,000円安くなります。 所得税51,000円 住民税41,000円 |
税金は約143,000円安くなります。 所得税102,000円 住民税41,000円 |
| 100万円以下 ※給料なら年収165万円以下 |
税金は約63,000円安くなります。 所得税22,000円 住民税41,000円 |
税金は約82,000円安くなります。 所得税41,000円 住民税41,000円 |
税金は約123,000円安くなります。 所得税82,000円 住民税41,000円 |
|---|---|---|---|
| 105万円以下 ※給料なら年収170万円以下 |
税金は約48,000円安くなります。 所得税17,000円 住民税31,000円 |
税金は約62,000円安くなります。 所得税31,000円 住民税31,000円 |
税金は約93,000円安くなります。 所得税62,000円 住民税31,000円 |
| 110万円以下 ※給料なら年収175万円以下 |
税金は約33,000円安くなります。 所得税12,000円 住民税21,000円 |
税金は約42,000円安くなります。 所得税21,000円 住民税21,000円 |
税金は約63,000円安くなります。 所得税42,000円 住民税21,000円 |
| 115万円以下 ※給料なら年収180万円以下 |
税金は約18,000円安くなります。 所得税7,000円 住民税11,000円 |
税金は約22,000円安くなります。 所得税11,000円 住民税11,000円 |
税金は約33,000円安くなります。 所得税22,000円 住民税11,000円 |
| 120万円以下 ※給料なら年収約185万円以下 |
税金は約9,000円安くなります。 所得税3,000円 住民税6,000円 |
税金は約12,000円安くなります。 所得税6,000円 住民税6,000円 |
税金は約18,000円安くなります。 所得税12,000円 住民税6,000円 |
| 123万円以下 ※給料なら年収188万円以下 |
税金は約5,000円安くなります。 所得税1,500円 住民税3,000円 |
税金は約6,000円安くなります。 所得税3,000円 住民税3,000円 |
税金は約9,000円安くなります。 所得税6,000円 住民税3,000円 |
| 123万円超え ※給料なら年収188万円超え |
税金は0円安くなります。 所得税0円 住民税0円 |
税金は0円安くなります。 所得税0円 住民税0円 |
税金は0円安くなります。 所得税0円 住民税0円 |
※上記は1年間の金額です。人数が増えるとさらに税金が安くなります。
※税金は税金保険料シミュレーションで計算。
※個人事業主は個人事業主の税金シミュレーションで計算できます。上記の年収と結果が変わるので気をつけましょう。
※ちなみに、子供の給与収入が年収150万以下なら安くなる金額は扶養控除と変わりません。たとえば子供の年収が123万以下の場合、税金は約7.7万円安くなりますが、子供の年収が150万以下であっても税金は約7.7万円安くなります。
※こんなページもみられています
大学生は150万まで稼いでも扶養を外れない?

特定親族特別控除は年齢が19歳以上23歳未満の特定親族がいるひとが利用できます。
※特定親族になる条件は下記のとおりです。
特定親族とは、合計所得が58万超~123万以下である19歳以上23歳未満の親族のことです。
くわしい条件は以下のとおりです。
下記にすべてあてはまる方を特定親族といいます。特定親族がいるなら特定親族特別控除が利用できます。
※出典:国税庁扶養控除生計を一にするの意義
※参照:国税庁令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

合計所得58万超えとは
例えば、あなたの子供(大学生)の収入がアルバイトの給与収入のみであり、1年間(1月~12月末まで)の収入が125万円のとき、給与所得は60万円となります。
それ以外に所得がないので合計所得金額は60万円となります。この場合、合計所得58万を超えているのであなたの子供は特定親族の対象になります。
給与所得控除については給与所得とはを参照。
※給与所得は給与所得シミュレーションで計算できます。
※2025年は給与所得控除の最低保証額が10万円引き上げされました。
※給料のほかに所得がある場合は下記の記事を参照。
所得58万円を超えると扶養してくれている親族の税金が上がる?

合計所得が58万円までは扶養親族の対象であり、合計所得が58万円超~123万以下は特定親族の対象となります。
※19歳~22歳の場合限定です。
そして、合計所得58万を超えても合計所得85万(給与収入のみなら150万)以下であれば親の税金は増えません。
※2024年の税制までは103万円(つまり、給与所得48万円)が扶養のボーダーラインでした(くわしくは2025年の税制を参照)。
しかし、扶養親族の対象から外れると人によっては下記のデメリットを受けることになります。
▶手当が支給されなくなる?
※親が会社独自の福利厚生(扶養手当や家族手当)などをもらっている場合、子供の年収によっては手当が支給されなくなることがあるので確認しておきましょう。
※会社によっては子供がいると年間6万~12万円くらい手当がもらえます。
▶ひとり親の対象外?
ひとり親の家庭の子供が扶養親族の対象から外れると、「ひとり親控除」が使えなくなる場合があります。そうなれば親の税金が増えてしまいます。
※一人っ子であればひとり親控除が使えなくなります。
※くわしくは母子家庭の子供はいくらまでバイトOK?扶養を外れると?を参照。
※ひとり親控除についてはひとり親控除とは?わかりやすく解説。を参照。
▶住民税非課税じゃなくなる?
親が住民税0円(非課税)だった場合、子供が扶養親族の対象から外れると、親に住民税が課税される場合があります。
※くわしくは母子家庭で住民税が非課税になるには?子供2人~3人の場合を参照。
▶ほかには?
子供が扶養親族の対象から外れると奨学金や多子無償化制度に影響が出る場合があります。
※くわしくは日本学生支援機構でご確認ください。

学生であれば勤労学生控除を利用して税金を安くすることが可能です。しかし、合計所得が85万円(給与収入で150万)を超えてしまうと勤労学生控除の対象外となります。
たとえば、年収150万で勤労学生控除を利用しないと住民税が約2万円くらい高くなってしまいます。
※くわしい条件等については勤労学生控除とは?を参照。
18歳以下や23歳以上で年収123万を超えてしまえば扶養親族から外れて親の税金が増えてしまいます。
「150万まで親の税金が増えない制度」である「特定親族」にあてはまるのは19歳~22歳限定なので注意しましょう。
子供が103万超えたら親はいくら払う?学生バイトは年収いくらがおすすめ?
では次に、控除を利用したときの所得税の計算はどうやるのかについて下記で説明していきます。年収から所得税の計算過程をチェックしておきましょう。

給料をもらっている人(会社員など)が特定親族特別控除を利用したとき、税金がどれくらいになるかシミュレーションしてみましょう。
ここでは会社員の夫が大学生の子供を扶養している場合として計算していきます。
①まず特定親族の対象になるかどうか。
たとえば大学生の子供の収入が給与収入(アルバイト)のみであり、1年間の収入が140万円のとき、給与所得は75万円となります。
子供の収入は給与収入のみなので、合計所得金額は75万円となります。したがって、子供は特定親族の対象となります。
②夫の給与所得の計算
ここから夫が特定親族特別控除を適用したときの計算
たとえば夫の収入が給与収入のみであり、年間収入が350万円のとき、給与所得は、
となります。給与所得のほかに所得がないので、これが総所得金額となります。
③次に課税所得を計算する
総所得金額は計算できたので(237万円)、次に課税所得を算出します。課税所得は、
となります。所得控除を204万円(
※子供の合計所得が75万円なので特定親族特別控除額は63万円になります。
※控除額の計算は上記表を参照。
となります。
④所得税の計算
課税所得がわかったので所得税を計算します。所得税は
となります。課税所得195万円以下は税率が5%なので、所得税は、
となります。
もし控除を利用しなければ税金はどうなる?
特定親族特別控除63万円を利用しない場合、そのぶん課税所得が増えるので、
となり、控除を申請したときと比べて税金の負担が重くなってしまいます。なので、特定親族特別控除が利用できるなら 年末調整または確定申告で申請しましょう。
※申請方法は下記で説明しています。
※こんなページもみられています
手取りと税金をパッと計算!シミュレーション
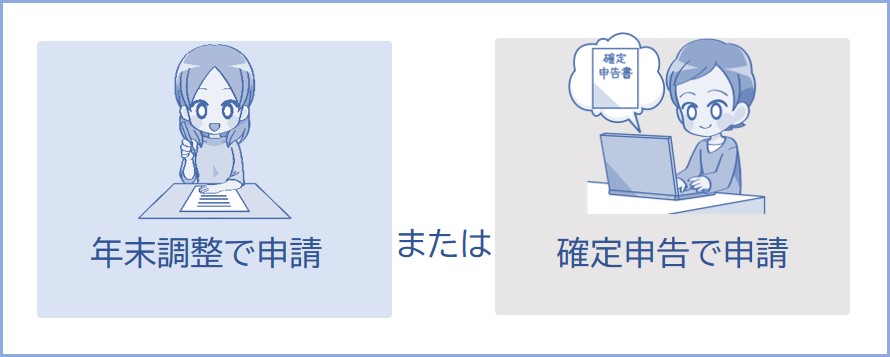
特定親族特別控除を適用するには年末調整で申請をしなければなりません。
特定親族がいる家庭にとってお得な制度なので、忘れないように申請しましょう。
※税金がいくらお得になるかは上記で説明しています。
年末調整の書類は10月~12月頃に勤務先から配布されるので、その書類に記入して提出しましょう。
以下のページで年末調整の書き方と申請方法を説明しています。控除を利用する方はぜひ参考にしてみてください。
※子供のアルバイト収入の書き方なども説明しています。
控除の申請方法については、特定親族特別控除の申請(年末調整の記入例)を参照。
年末調整の書き方については、年末調整の書き方見本・記入例を参照。
※確定申告の申請方法については後日記載します。
特定親族特別控除を利用する方は申請を忘れないようにしておきましょう。学生の年収と税金の関係などについては下記の記事で説明しているのでチェックしておきましょう。
 しらべたい内容を探す
しらべたい内容を探す
















